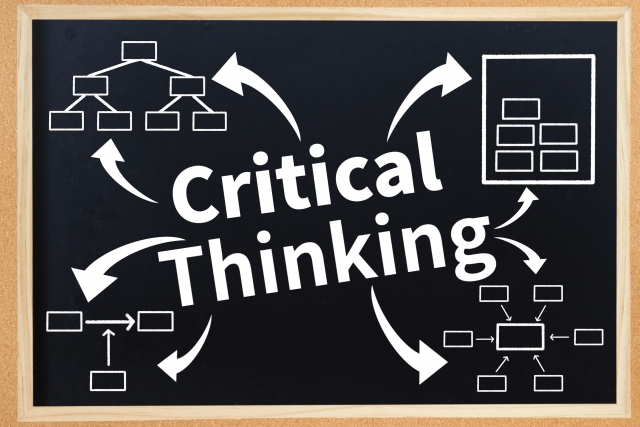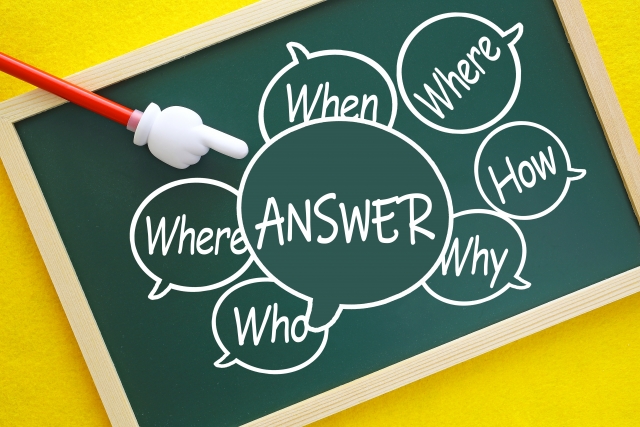
おはようございます。
本日は思考の話を書いていきたいと思います。クリティカルシンキングは昔から存在する思考法ではありますが、実際に使用しながら業務を進めているのはごく一部のエリート層である気がします。学校では、解法や内容の暗記がメインの授業になりますので、「疑う」ということが身に付きません。
疑うというと日本人はアレルギーが出そうですが、相手を疑うという事ではなく、その事象が本当かどうかを疑うことが必要なのです。この考え方がクリティカルシンキングであり、大変重要な思考法になります。
クリティカルシンキングができるようになると、知識の定着も早くなりますし、思考力が高まります。
知識の定着に関しては、その事象が起きた事実や知識が「なぜ」起きたかという問いを自分ですることで、その周辺知識も同時に獲得できます。例えば、「クワガタは昆虫である」という答えがあったとして、「なぜ」をそこから考えるならば、「昆虫ってそもそもなんだろう」、「クワガタが昆虫である定義はなんだろう」、「昆虫は動物となにが違うんだろう」など多くの疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。すると、「クワガタは昆虫である」から多くの知識がつながり始めます。クリティカルシンキングは知識の幅を広げます。疑問が浮かばない方もこの思考を繰り返すと、自然に疑問の出し方が身についてきます。
思考力という面でも、事象に対して多角的に捉えることができるようになるメリットも存在します。さきほどの例でも「クワガタは昆虫である」という事をそのまま鵜呑みにするのか、本当に昆虫なのかを問うことは大きな差がでます。世の中には事実と異なることが多く存在します。人生という長いレールの上で学んだ知識と違う事実が出てくることは、往々にして存在します。現代の「正しい・常識」は科学的に証明できるものもあれば、統計的に事実なのではないかというレベルのものなど様々あります。つまり疑う余地があることが多いのです。
クリティカルシンキングを学び、色々な角度から物事をみる力や、俯瞰する力を身に着けることがイノベーションを生む力につながりますし、どの時代でも対応できるような人間になれると思います。
注意点として対人関係の中で、露骨に相手を疑ってしまうのはよくないです(笑)もし会話の中で疑問に思うことがあれば覚えておいて、後で自分なりに深堀していくことがベストです。疑うことは「悪」ではないです。そもそも誰かに対して疑いを持つのではなく、その事象や知識に対して疑問を持つのです。
世の中の偉人は、みなその時の常識を壊してきました。常識をそのまま受け入れるだけではなく、常識からさらに一歩踏み込んだ知見を手に入れると生きやすくなると考えます。
これは子供の教育に使えるとも思います。子供は小さい頃はすべてに対して興味を持ち、なぜなぜ攻撃を繰り出し来ます。この時の子供の知識を吸収するスピードはとんでもなく、自発的に知識を得ようとしていることがこの結果を生んでいると考えます。学校教育の中でなぜを問う機会は圧倒的に減りますので、ご家庭ではなぜなぜ攻撃を親がしてみるのもいいかもしれません。ウザがられない程度に(笑)
クリティカルシンキングを学ぶことで成長できることは理解できたかもしれません。一番役に立つことは知識が増えることもあり、詐欺などに引っ掛かりにくくなります。「疑う」を忘れないことで違和感を感じることができます。自分もしくは子供には、この思考法を学ばせることをおすすめします。
最後に私が好きなアインシュタインの言葉を送ります。
「常識とは 18 歳までに身につけた偏見のコレクションでしかない。」
では。