おはようございます。
本日は私の趣味でもあります、「料理」について書いていきたいと思います。料理をしっかりするようになって、仕事の生産性が爆上がりしていることに気が付きました。なぜ上がっているのかを考えてみることで、見えてきたものがあるのでここで書いていきたいと思います。
おいしいものを作ろうとする企業理念が生まれる
料理を作る自分を会社に見立てると、美味しい料理を提供する目的をもった会社になります。それが毎回料理を制作する上での理念になり、モチベーションになります。なにかに取り組むときに、モチベーションを高めてから取り組んだりやりがいを作ると、今まで以上にいい成果物を作ることができます。何かに取り組むときの姿勢が身に着くような気がしています。
生産計画の立案
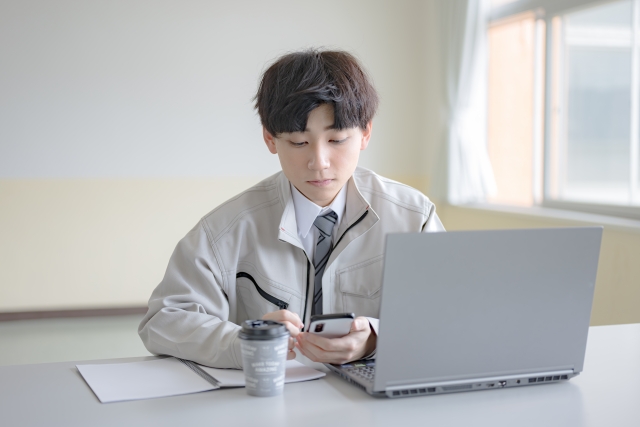
料理を制作する上でまずしなければならないのは、どんな商品(料理)を生産するかどうかです。商品を選定して、仕入れをしないといけません。どこで材料を仕入れて、どれだけの量が必要になるのか、在庫で対応可能か、代替品で対応できるかなどを考えないといけません。ここで学ぶべきは過剰在庫にならないように、いかに最低限の出費で最大限のプロダクトを作るかどうかです。
もうひとつ考えなければならないのは、生産計画です。料理はひとつだけではありません。同時に3~4種類の商品を平行して生産しなければ、効率のいい生産とは言えません。どの料理にどれだけの時間がかかるかをあらかじめ予想し、作り始める料理をどれにするのかを考え、ほかの料理にとりかかる最適な順番を考えます。このときにコンロの数や、電子レンジ、オーブントースターなどの機器を効率的に稼働させることも考えます。
料理を行う上で理想の生産終了状態とは、すべての料理がほぼ同時に作り終わる状態です。常にそこを目指して、生産計画を考えます。
実際の仕事でも、このような計画を立てることは非常に有効であり、順序だてて考える癖がつきます。本当におすすめです。
食器洗いから学ぶ日本式生産システム

これはトヨタをはじめとする工業化社会で日本が躍進したシステムです。いかに効率的に生産を行い、無理・無駄・ムラをなくすことです。
食器洗いにもこれが応用できると思っています。それは、洗う順番の効率を最大化することです。どのようなことかといいますと、食器にもすぐに落ちる汚れとすぐ落ちる汚れが存在します。例として、ごはんがついた食器はごはんが固まっている可能性が高く、シンクの水につけておかないと取れません。カレーのルーなども同様に、時間がたつととれにくくなります。
なのでこれらはまず水につけておきます。この間にほかの食器を洗浄します。この時の洗う順番も大事になり、大きいものから洗います。理由はシンクを占領しているものを先に洗い、スペースを確保することで生産性が上がります。
すべて洗い終わったら、水につけておいた洗い物を始めて終了となります。
結論
どうですか?料理もこのように考えるとすごく仕事に役立つことばかりではないでしょうか。究極のマルチタスクだと思います。マルチタスクが苦手な人のトレーニングになりますし、計画をしっかり立てることでシングルタスクとしても処理が可能になります。
料理の考え方を変えるだけでも、とても有意義な経験が積めると考えています。
何より自分で美味しい料理を低価格で作れるようになったら、それこそコスパ最高ですよね。男性の方も料理をすることをおススメします。奥様の評価も爆上がりですよ。ただし、後片付けもやりましょう。作りっぱなしは一番最悪ですよ(笑)
では。




